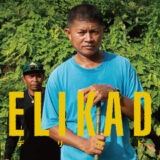ノー・アザー・ランド 故郷は他にない
パレスチナとイスラエルー立場を超えて手を取り合う
ふたりの若きジャーナリストに、世界中が声援と喝采!!
イスラエルによる破壊と占領が今まさに進行している、ヨルダン川西岸のパレスチナ人居住地区<マサーフェル・ヤッタ>。この現状をカメラに収め世界に発信することで故郷の村を守ろうとするパレスチナ人青年バーセル・アドラーと、彼に協力しようとその地にやってきたイスラエル人青年ユヴァル・アブラハームによる決死の活動を、2023年10月までに渡って記録。住民たちが目の前で家を壊され強制的に追放される不条理な現実を、緊迫の映像であぶりだす。
しかし惨状の中でも、同じ年齢の青年2人が共に過ごし対話を重ねることで、政治的背景や立場を越えた“命がけの友情”が生まれる奇跡的な瞬間を、本作はエモーショナルに映し出していく。自由のために強大な力に立ち向かい、支え合う彼らの姿は、「どうしたら人は分かり合えるのか?」という問いへの一筋の希望を私たちに与えてくれるに違いない。
監督は彼らを含むパレスチナ・イスラエル両国の若き映像作家兼活動家の4人。「イスラエル人とパレスチナ人が、抑圧する側とされる側ではなく、本当の平等の中で生きる道を問いかけたい」という強い意志のもと製作された。ベルリン映画祭では最優秀ドキュメンタリー賞と観客賞をW受賞し、観客によるパレスチナ連帯の大合唱や監督の受賞スピーチが話題となる一方、イスラエル擁護の立場を取るベルリン市長などがそれを強く非難。今なお世界中で大きな論争が続くなか監督たちは精力的に活動を続けている。各国の映画祭で絶賛を集めすでに30の賞を獲得。2025年の第97回アカデミー賞[長編ドキュメンタリー賞]も受賞している。
それでも僕たちは この現実を変えたい
ヨルダン川西岸地区のマサーフェル・ヤッタで生まれ育ったパレスチナ人の青年バーセルは、イスラエル軍の占領が進み、村人たちの家々が壊されていく故郷の様子を幼い頃からカメラに記録し、世界に発信していた。そんな彼のもとにイスラエル人ジャーナリスト、ユヴァルが訪れる。非人道的で暴力的な自国政府の行いに心を痛めていた彼は、バーセルの活動に協力しようと、危険を冒してこの村にやってきたのだった。同じ想いで行動を共にし、少しずつ互いの境遇や気持ちを語り合ううちに、同じ年齢である2人の間には思いがけず友情が芽生えていく。しかしその間にも、軍の破壊行為は過激さを増し、彼らがカメラに収める映像にも、徐々に痛ましい犠牲者の姿が増えていくのだった―。
参考 映画『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』公式ホームページ
イベントの開催概要
| 日 時 | 2025年 9月 2日(火) 19:00〜20:40(開場18:30) |
| 会 場 | 大竹財団会議室 東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル11階 八重洲地下街24番出口・右階段すぐ |
| 交 通 | 京橋駅 日本橋駅 |
| 参加費 | 一般=500円 学生=無料 |
| 対 象 | 一般(どなたでも参加可能です) |
| 定 員 | 22名 要予約 |
| 主 催 | 一般財団法人大竹財団 |

Ⓒ2024 ANTIPODE FILMS. YABAYAY MEDIA
上映会後の感想
《映画の感想》
ガザの現状のことも考えると夢も希望もないです。ユヴァルらの存在とこの二人の友情がこの映画の唯一の救い。
《もっとも印象に残ったシーン》
バーセルが「熱くなりすぎだ。君は10日間でいなくなるけど、何十年と続いている問題なんだ。すぐには解決しないよ」とユヴァルに車中でクールダウンさせるシーン。10日間という言い方にはやや棘があったけど、この理不尽すぎる状況で、20代半ばの青年がこんなにも忍耐強くいられるのかと驚いた。
《映画の感想》
見逃した映画だったので、心して鑑賞いたしました。パレスチナの状況は、ニュースなどで断片的に知っているように思っていましたが、現地はもっと、もっと過酷で悲惨な暮らしをパレスチナの人びとに強制していると認識しました。今現在暮らしている住まいを、突然、理不尽に破壊され、抵抗すると武器で脅されるだけでなく、しばしば殺害におよぶという。この映画に出ていたパレスチナの人も映画公開の後、入植者に殺害され、共同監督のハムダーンも暴行を受けたと、報道がありました。映画を観て、いちばん感じたのは、ふつうに流されているニュースは、信用ならないということです。
《もっとも印象に残ったシーン》
半身不随になった病人を、洞窟で看病しなくてはならない状況を描いたところ。
《映画の感想》
スマホとハンディカムの実写で構成されたこんなドキュメンタリーを観たのは初めてです!! それ故に、起きてい理不尽な現実に呆れ、怒りが湧き上がります。日々報道されるパレスチナの、ガザの画像だけでは知ることができない現場のリアルを届けてくれた2人と関係者の勇気を讃えたい。
《もっとも印象に残ったシーン》
ユヴァルが「じゃあ帰るよ」とバゼルに告げる時の無力感と罪悪感の入り混じったシーン。
《映画の感想》
イスラエルの横暴はあまりにもひどすぎる。元は社会福祉団体だったハマスがテロ組織に変貌したのもわかる気がする。逆にこんな過酷な状況で前向きに生きられる人すごすぎるでしょ。
《もっとも印象に残ったシーン》
ユヴァルがバーセルに「今度は君がうちに来いよ」的な話をする場面。優しさから出た言葉ながらとても残酷な会話だ。この状況でそんな未来を想像できるないでしょ。バーセルは猛勉強をして大学を出てもろくに職にもありつけない。日々スマホに向き合うしかない、何もやることがない。息が詰まるような牢獄のような不自由な毎日。自分がユヴァルだったらバーセルになんて声をかけてあげればいいんだろうかと自問する。
《映画の感想》
パレスチナ人の家や学校を破壊するイスラエル軍や入植者の横暴ぶりに強い怒りを覚える。やりたい放題、まさに無法地帯だ。80年ちょっと前の戦中の日本軍や移民した人たちも中国やアジア諸国でこうだったんだろう。でも戦争や占領下だから仕方がないでは済まされない。ベルリン映画祭やアカデミー賞を受賞してこのありえない状況が世界に発信されても状況が何一つ変わらない異常さ。世界は狂ってる。こんなにも理不尽に溢れている。日本にいたらここまで理不尽なことは起こらない。いかに自分たちが恵まれているのかということも思い知らされました。
《もっとも印象に残ったシーン》
軍事演習中の戦車のすぐ脇に小さな子どもたちがいるシーン。